「トランプ関税が発動されたって本当?」「また株価が暴落した…もう投資はやめるべき?」
そんな不安が頭をよぎっている方へ。
かつての「トランプショック」も記憶に新しいですが、2025年現在もアメリカを中心に政治リスクが投資市場を大きく揺さぶっています。
私は長期のインデックス投資と暗号資産への積立投資を並行して行っている個人投資家ですが、こうした相場の波に直面するたび、「やめるべきか?」「続けるべきか?」という迷いは多くの方が抱くものだと実感しています。
この記事では、感情ではなくデータと原則に基づいた判断のヒントをお伝えします。トランプショックのような混乱期において、私たちが取るべき姿勢とは何か?一緒に考えていきましょう。
①:歴史は「混乱=売り時」ではないと教えてくれる
まず押さえておきたいのは、過去の市場の歴史は「混乱があった時期ほどチャンスもあった」ということです。
たとえば:
- 2008年リーマンショック
- 2020年コロナショック
- そして2018年のトランプ関税発表に起因した米中貿易摩擦(いわゆるトランプショック)
これらの直後、確かに株価は短期的に大きく下落しました。ですが、長期的に見ればその後の回復と上昇トレンドの方が遥かに大きかったのです。
一時の下落でやめてしまう=安値で売ることになりかねず、それは投資の鉄則に反する行動です。
市場が揺れている今こそ、「自分は短期で儲けたいのか?長期で育てたいのか?」を問い直す良い機会なのです。
②:政治リスクは常にある。だからこそ「分散と継続」が重要
トランプ前大統領の動きに限らず、政治の混乱・選挙・政策変更は投資市場に少なからず影響を及ぼします。
- 関税の引き上げ → 輸出関連株の下落
- 国際摩擦の高まり → 金融市場の不安定化
- 金利政策の急変 → 債券・株式の変動
しかし、それらを毎回完璧に読み切って売買で利益を上げ続けることは、プロでも難しいのが現実です。
だからこそ、私たち個人投資家がとるべき基本戦略はシンプルです:
- 広く分散されたインデックスファンドに投資する
- 毎月一定額を積み立てる(ドルコスト平均法)
- 10年、15年というスパンで運用を続ける
政治は変わる。相場も揺れる。けれど積立と分散は裏切らない。これが、長期投資家としての基本スタンスです。
③:不安定な今こそ“資産防衛”としての暗号資産も検討を
投資に不安を感じるタイミングで「やめよう」と考えるのは自然な反応です。ただし、今のようなインフレ懸念・通貨不安・金利上昇が重なる状況では、「現金で持っておく=リスクゼロ」とは言い切れません。
こうした局面で注目されるのが、ビットコインや金(ゴールド)などの“価値保存資産”です。
ビットコインは「デジタルゴールド」とも呼ばれ、中央政府の影響を受けにくい特性を持ちます。もちろんボラティリティは高いですが、保有資産の数%程度を分散先として組み込むことで、全体のリスクヘッジになる可能性があります。
私は、毎月少額ながらビットコインも積立していますが、これは「値上がりを狙っている」だけでなく、万が一に備えた“通貨リスクのヘッジ”という意味合いが強いです。
株式市場が混乱しても、異なる性質を持つ資産に分散しておけば、資産全体のダメージを和らげることができます。
④:「投資をやめる」ではなく「戦略を見直す」という選択肢を
最後に大切なことをお伝えしたいのですが、投資に不安を感じたとき、最もしてはいけないのは“感情で売ること”です。
たとえば、以下のような選択肢も検討してみてください:
- 積立額を一時的に減らして、精神的負担を軽くする
- 株式100%のポートフォリオを債券や現金比率のあるバランス型に見直す
- 株式の中でも値動きの大きい個別株から、インデックス中心に切り替える
- 暴落時の“買い増し資金”として現金を一定額残しておく
つまり、「全部やめる」ではなく、リスク許容度に応じた“戦略の微調整”が賢明な判断なのです。
そして、自分の資産運用が「10年後の未来を守るためのもの」であることを再確認できれば、不安にも揺るがない“軸”ができてきます。
まとめ:トランプショックでも、未来を信じて積み上げよう
政治の混乱や報道のインパクトで、「やっぱり投資って怖い」「やめた方がいいかも」と思う気持ち、よくわかります。けれど、不安定な時期こそ“思考停止で撤退”ではなく、“冷静に見直し”をするタイミングです。
トランプショックのような短期的な混乱は、長い投資人生の中では何度も訪れます。そのたびにやめてしまっては、資産形成は進みません。
コツコツと、でもしっかりと「続ける」こと。
自分にとって心地よいリスクに調整すること。
そして、ニュースに振り回されない“自分の軸”を持つこと。
それが、個人投資家として最も大切な心構えです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
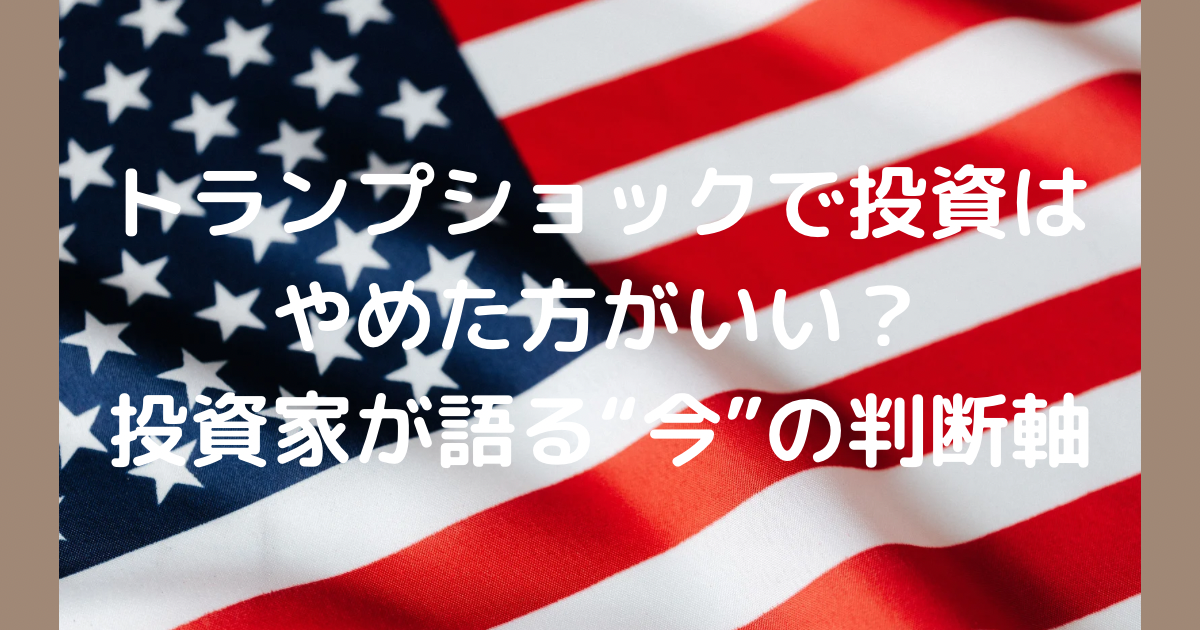

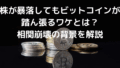
コメント