2025年春、いわゆる「トランプショック」によって世界の株式市場が急落しました。再び打ち出された保護主義的な関税政策や地政学リスク、インフレ圧力の再燃によって、多くの投資家が混乱に陥る展開となりました。
しかし、このショックに際してひとつ異例の動きを見せた資産があります。そう、ビットコイン(BTC)です。
従来は株価と連動してリスク資産の一つとみなされてきたビットコインが、今回の下落相場の中でほとんど値崩れせず、むしろ価格を維持または上昇する場面さえあったのです。
今回は、個人投資家としてインデックスと暗号資産の両方に投資している筆者が、「なぜビットコインは株と逆の動きを見せたのか?」というテーマを3つの観点から解説します。
①:ビットコインは“リスク資産”から“価値保存資産”へ変化しつつある
かつてのビットコインは、ボラティリティ(値動きの大きさ)が激しく、リスク資産の代表格のように扱われていました。特に株式市場が下落する局面では、ビットコインも一緒に売られる動きが多く、「株と相関が高い」と言われていました。
ところが近年、この見方が大きく変わりつつあります。
背景にあるのは:
- ビットコインETFの承認による機関投資家の流入
- 半減期による供給制限(2024年4月実施)
- 世界的なインフレ圧力と通貨不安の高まり
これらが重なり、ビットコインが「リスク資産」ではなく、価値を守るための資産(ストア・オブ・バリュー)として再評価されてきているのです。
金と同様に、「金融不安・インフレ・地政学リスク」などの状況下で“逃避資産”として買われる傾向が強まり、「株と連動する」ではなく「株と逆の動きをする」場面が増えてきています。
②:機関投資家の長期保有が価格の安定性を支えている
従来、ビットコイン市場は個人投資家中心で、価格も感情的な売買に振り回されやすい傾向がありました。
ところが2024年以降、現物ビットコインETFの登場により、年金基金や保険会社、ファミリーオフィスなどの長期保有を前提とした機関投資家が本格参入してきています。
これは市場にとって非常に大きな意味があります。
なぜなら:
- 大量の売買をしない
- 長期保有前提のため、価格が多少上下しても売らない
- 市場全体に「安心感」を与える
これにより、以前のように「悪材料が出た瞬間に暴落する」ような展開は起こりにくくなり、株価の急落にも冷静に耐える市場構造ができつつあるのです。
特に今回のトランプショックでは、「株は売られても、ビットコインはそのままホールド」という機関の動きが相場の支えになったと考えられています。
③:「株式=国家依存」「ビットコイン=非中央集権」の違いが表れた
今回のような政治的混乱の中で、あらためて見直されているのが、資産の本質的な性質の違いです。
株式は基本的に企業の成長を信じて投資するものであり、その企業の収益は国家の政策や税制、国際関係の影響を強く受けます。
たとえば:
- 関税が上がれば輸出企業の業績が悪化
- 利上げが続けば借入コストが増加
- 国際摩擦が高まれば株式市場にリスクオフの風
一方、ビットコインは非中央集権・グローバルなデジタル資産であり、どの国家にも依存していません。ある意味で「通貨の外側にある資産」とも言える存在です。
今回のショックで「国家政策が原因で株が急落する」状況に対して、ビットコインは比較的冷静に推移しました。
これは、ビットコインが「国家の外にあるセーフティネット」になりつつあることを象徴する現象だと筆者は捉えています。
まとめ:相関崩壊は「ビットコインの成熟化」のサイン
今回のトランプショックによって、株とビットコインが必ずしも同じ方向に動かないことが、改めて示されました。
この“相関崩壊”は、決して異常ではなく、むしろ:
- 投資家層の変化(個人から機関へ)
- 資産としての認識の変化(リスク資産→価値保存)
- 構造的な資産性の違い(中央依存 vs 非中央)
といった、ビットコインの「資産としての成熟」が進んでいる証とも言えるでしょう。
もちろん、ビットコインには依然としてボラティリティの高さや法規制リスクなど課題もあります。ですが、今回のような場面で資産分散の一環として「持っていてよかった」と感じた投資家も多いはず。
あなたのポートフォリオに、“中央に依存しないもう一つの資産”をどう組み込むか――今こそ、真剣に考えるタイミングかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。

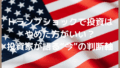

コメント